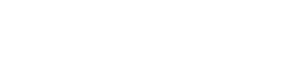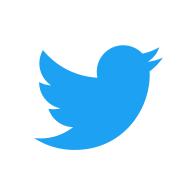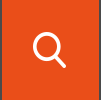目次ほたる 「記憶のはしっこ」#16
8 Photosモデル・ライターとして活動する20歳、目次ほたるが写真を通して、忘れたくない日々の小さな記憶をつなぐ連載「記憶のはしっこ」の16回目です。
目次ほたる 「記憶のはしっこ」#16
8 Photosモデル・ライターとして活動する20歳、目次ほたるが写真を通して、忘れたくない日々の小さな記憶をつなぐ連載「記憶のはしっこ」の16回目です。

カメラを持って散歩をする機会が増えてから、人生で初めて自分でスニーカーを買った。
幼い頃は親に買ってもらっていたし、学生時代は学校の指定靴があったし、働き始めてからはパンプスを履くことが多くて、運動に適した靴を買う機会がなかったのだ。
今までは、散歩のときは比較的歩きやすいブーツなどを選んで履いていたけれど、カメラを持って散歩となると、そうはいかない。写真を撮るのに夢中になるからか、歩く距離が普段の倍以上になったからだ。(おかげで、この連載が始まってから、少し痩せた)
そのため、どんなに歩きやすいブーツでも、土踏まずが痛くなり、かかとの皮が擦り切れる。どうしてこんなに痛い思いをしながら歩かなければいけないんだろう、と頭を悩ませるばかりだった。
そして、ある日突然気がついたのだ。
「こんな犠牲を伴うくらいなら、スニーカーを買えばいいじゃないか」と。
逆に、どうして今まで買っていなかったのだろうか。固定概念は恐ろしい。
そして購入したスニーカーを履いて外に出ると、あら不思議。
身体のどこも痛くならず、好きなだけ歩けるのだ。
「スニーカーって、こんなに素晴らしいものだったのか!」
誰もが知っている運動靴の魅力を初めて知った日だった。

街中を撮っていると、私が撮りたいのは、「写真」なのか「風景そのもの」なのかがわからなくなる。
今まで見てきたのであろう記憶のなかの理想の写真を、カメラを使って再現することは、果たして「自分が撮っている」ことになるのだろうか。

プールを見ると、中学生のときに水泳の授業でバタフライを習った日のことを思い出す。
私は運動全般が大の苦手で、体育の授業を心の底から憎んでいた。
この世から体育の授業がなくなれば、自分もいくぶんか幸福になれるだろうと本気で思っていたのだ。
とくに苦手だったのは、水泳の授業だ。公衆の面前で水着を着なければいけないし、冷たい水に入って、一生懸命泳げを言われる。新しい拷問の一種だと思っていた。
泳ぎも、もちろん下手くそで、泳ぐいうより「水の中で足掻いている」という表現のほうが正しかったと思う。
そんなある日、バタフライの授業が行われた。
私がいつものように泳ぎ(のような動き)をしていると、先生が私にこう言い放ったのだった。
「お前のバタフライは、なんとういうか、趣旨が違うな」
と。泳ぎの趣旨とはなんだろうか?と思わなくもなかったが、
先生の言う意味がなんとなくわかってしまい、余計に腹立たしかった。
あの先生の言葉はおそらく一生忘れない。

あと70年くらいは生きられるとして、「あと70年生き続ける」と考えると長く感じるけれど、「あと70回しか秋を迎えられない」と考えると、なんだか短い気もしてくる。

ピアニカ、いつから吹いていないだろう。

目黒にある庭園美術館を観に行った。
中学生くらいから芸術に興味を持ち始め、今でもこうして定期的に美術館へ足を運ぶのが、趣味の1つだ。
数ある美術館のうちで庭園美術館の持つ面白さは、建物自体も芸術品として楽しめるところだ。
というのも、旧朝香宮邸といって、皇室財産に認定されている古い邸宅をそのまま改築して、美術館として使われているから。
本館の隣には、広い庭園も残されており、それが「庭園美術館」と名がついた由縁だそうだ。

私は美術館そのものに興味があって訪れたため、どんな展示がやっているのかを調べもしなかった。
美術館のチケット売り場を覗いてみると、「生命の庭」展と書かれており、名前からしていかにも難しそうだったので一瞬怯んだものの、チケット売り場の女性に「それ以外の展示はやっていない」と言われたため、とりあえず入ってみることにした。
「生命の庭」展は、8人の芸術作家によって、自然と芸術、そして人間社会との関わりについて問う作品が展示されていた。
最初からそんな意味合いがわかったわけではない。
途中までチンプンカンプンだった作品も、時間をかけて見て回るうちに、展示のテーマや作家たちの思いをなんとなく理解しつつある自分に気がついたのだ。
私が思うに、この瞬間が、美術館の醍醐味だ。
必死になって作品に対峙すれば、必ず自らがいかに無知であるか気づき、その対価に、今まで触れることのなかった新しい世界に遭遇できる。
都会のなかで、庭園とともに静かに佇むその場所は、私のなかに潜む自然を教えてくれたような気がした。

撮影・文 目次ほたる