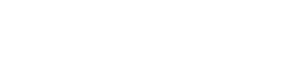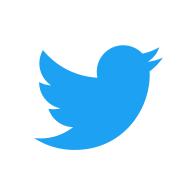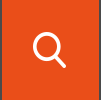目次ほたる 「記憶のはしっこ」#22
6 Photosモデル・ライターとして活動する20歳、目次ほたるが写真を通して、忘れたくない日々の小さな記憶をつなぐ連載「記憶のはしっこ」の22回目です。
目次ほたる 「記憶のはしっこ」#22
6 Photosモデル・ライターとして活動する20歳、目次ほたるが写真を通して、忘れたくない日々の小さな記憶をつなぐ連載「記憶のはしっこ」の22回目です。

2020年12月26日。
クリスマスも終わり、世間があっという間に年末ムードに包まれるなか、私は目の前の鶏の丸焼きを口いっぱいに頬張っていた。
年末はなんだかんだと慌ただしい日々を送っており、クリスマスのお祝いをしている時間がなかった。
行事にあまり関心があるほうではないけれど、クリスマスといえば豪華な料理が登場する日。
チキンやケーキ、ピザやお菓子など、ハイカロリーな食べ物を「クリスマスだから」という言い訳で、たらふく食べられる素晴らしいイベントなのだ。
だから、どうしてもクリスマスっぽいことをしたかった(正しくは、行事に乗じてごちそうを食べる口実が欲しかった)私は、料理上手の家族に頼んで、鶏の丸焼きを作ってもらったのだ。
塩コショウを揉み込んで、一晩休ませた鶏の中に野菜やもち米を詰めて、オーブンで焼く。
家族が丁寧に作ってくれたそれがたまらなく美味しくて、「おいっしいいいいい」と叫びながら貪るように食べた。
寒い部屋をストーブで温めながら、一足遅れて始まった我が家の聖夜。
「こんなに楽しいのだから、クリスマスは年中いつ開催してもいいじゃないか」
そんなことを考えながら、最後の肉を飲み込んだ。

クリスマスといえば、幼い頃にサンタさんにプレゼントをお願いした日のことを思い出す。
当時の私は、ファンタジー絵本にハマっていて、そのストーリーのなかに「虹色に光る魔法宝石」が出てきた。
それを見て、どうしても魔法の宝石が欲しくなった私はサンタさんにその虹色の宝石を頼んでみようと思ったのだ。さっそくサンタさんへプレゼントのお願いをする手紙を書き始めた私だったが、書きながら急に不安になってきた。
「宝石なんて高価なものをお願いしたら、サンタさんに悪い子だと思われて、来てもらえなくなっちゃうんじゃないか……?」と。
でも、虹色に光る魔法のなにかはどうしても欲しい。宝石は高価すぎるけれど、他の光る石的なもので代用できないか。そう考えた私は父にお祭りで買ってもらったビー玉のことを思い出した。ビー玉なら安そうだし、大丈夫かもしれない。
そうして、手紙の「宝石」と書いた部分を消しゴムで消して、「ビー玉」と書きかえ、「虹色の魔法のビー玉をください」とサンタさんにお願いすることにしたのだ。
やっと、あの魔法の宝石が手に入る。そう思って、ワクワクしながらサンタさんを待ったが、朝起きて枕元に置いてあったには虹色のビー玉ではなく、赤や青や黄色など、7色のビー玉が入った巾着袋だった。
今考えれば、サンタさんのプレゼント入手ルートには「虹色に光る魔法のビー玉」なんて流通していなかったのだろうと思うけれど、子どもの頃はそれにひどくがっかりしたのだ。
クリスマスになると、いつも虹色のビー玉を思い出して、一人で笑ってしまう。

年明け、2021年1月2日。
私たちは家族で集まって、新年の挨拶をしていた。
私は5人姉妹で、母を入れて6人家族なのだけれど、この6人が全員集まるのは実に5年ぶり。皆それぞれ結婚して子どもがいたり、恋人と暮らしていたりするものだから、この5年間なかなか集まれていなかったのだ。
今年はウイルスが心配だから感染の可能性を少しでも減らすために、母の職場の個室を借りて、小さな新年会が始まった。

テーブルにはみんなで持ち寄った食材や料理が並び、一気に豪華な食卓ができあがった
久しぶりに会う、家族全員は一人ひとりが5年前とは顔つきも雰囲気も変わっていて、時間の流れを感じさせた。それに、隣にはそれぞれのパートナーや家族が並んでいる。私たちは時間をかけて着実に変わりつつあるのだ。
私はその様子がどうしても残したくて、持てるカメラをすべて持って、たくさん撮った。
写真という「記憶を残す方法」を1つ知った私は、以前よりずっと幸せ者だと思う。

そういえば、今回の新年会で姉の息子に初めて会った。
高校を卒業してから、すぐに働きはじめていた私は甥っ子に会う機会がなく、あれよあれよという間に、甥っ子ももう2歳になっていたのだ。
「私もついにおばさんかぁ」
そんなことをつぶやきながら、甥っ子を撫でる。
かつて、一緒に暮らし、よく喧嘩をしていた姉が自分の息子を抱きかかえて「お母さん」の顔を向けているのが、なんだかとても不思議だった。
そして、私たちの母がそんな甥っ子を眺めている顔は、私たちのまえで見せる「お母さん」の顔ではなく、幸せに満ちた「おばあちゃん」の顔で。
月日が流れる間に、一人ひとりが新しい人生を築き上げ、家族が連鎖していく。
そのはじめの一歩を見た気がした。

撮影・文 目次ほたる